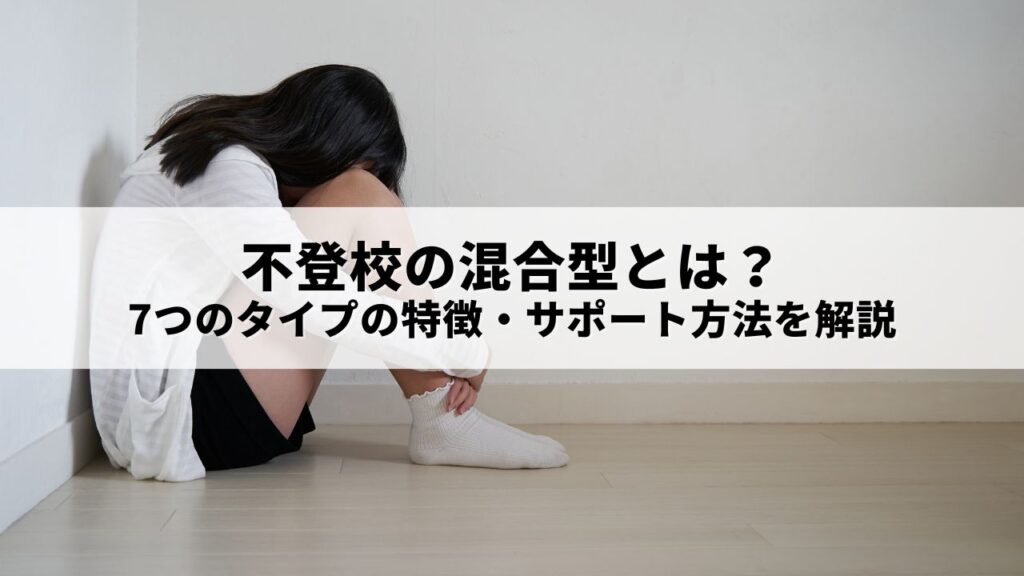不登校の混合型(旧「甘え依存型」)とは?7つのタイプの特徴とサポート方法を解説
近年、不登校になる児童が年々増加しており、その要因や特徴も一人ひとり異なります。
しかし、子どもがどのタイプに当てはまるのか、どのような対応をしていけば良いのか悩んでいる親御さんも多いでしょう。
この記事では、不登校の混合型やその他のタイプの概要と、混合型のサポート方法を解説します。
この記事を読むことで、それぞれの要因にあった適切な対応ができるでしょう。
TS assistは、児童発達支援・放課後等デイサービスに特化したコンサルタントとして、豊富な運営経験を活かした専門的な支援を提供いたします。200店舗以上のサポート実績に基づき、職員の信頼関係構築や業務効率化のための具体的な戦略を提案します。
各施設に合わせたカスタマイズサービスで、経営の安定と収益向上を目指しましょう。個別対応の細やかさと、Googleチャットを通じた迅速なコミュニケーションで、お気軽にご相談いただける体制を整えております。より良い療育の提供に向けて、TS assistはお客様の信頼できるパートナーであり続けます。
もくじ
不登校の混合型(旧「甘え依存型」)とは?不登校のタイプ別の概要
不登校は、混合型(旧甘え依存型)を含む7つのタイプに分類されます。
ここでは、タイプ別の特徴を詳しく解説します。
タイプ1:混合型(旧「甘え依存型」)
混合型(旧「甘え依存型」)は、友人関係のトラブルや学校での失敗など、さまざまな要因が重なって不登校になるタイプです。
このタイプの子どもの特徴は、以下のとおりです。
- 感情の変動が大きい
- 実際の年齢よりも精神的に幼い
- 忍耐力や自立心が育っていない場合がある
- 逃避、回避の傾向が強く、何かを最後までやり遂げた経験が少ない
- 自己主張が苦手で、他者との関係においてストレスを感じやすい
- 基本的な生活習慣が身についていない場合が多く、生活リズムが乱れている
混合型の子どもがストレスを感じると、情緒不安定になり身体的な症状が現れる場合があります。
しかし、深く落ち込む様子はなく、他者から見ると無気力な状態に見えるのがこのタイプです。
タイプ2:母子分離不安型(旧「分離不安型」)
母子分離不安型(旧「分離不安型」)は、特に小学校低学年の子どもに多く見られます。
このタイプの子どもの特徴は、以下のとおりです。
- 母親と離れることに強い不安を感じる
- 母親にべったりとくっつくなどの幼児退行現象が見られる
- 母親を独占しようと、父親や兄弟に対して敵意を向ける
- 母親が側にいると情緒が安定し、一緒に登校できたり友達と遊べたりする
母子分離不安型は、子どもの性格や母親との関係性、家庭環境などが原因として考えられます。
その他に、自閉症などの発達障がいのある子どもは、新しい環境への適応が難しく、母親への依存が強くなる傾向があります。
タイプ3:情緒混乱型(旧「良い子息切れ型」)
情緒混乱型(旧「良い子息切れ型」)は、真面目で几帳面な性格の子どもに多く見られます。
このタイプの特徴は、以下のとおりです。
- 感受性が豊かで内気な性格である
- 学校を休むことに対して強い罪悪感を抱き、身体的な不調を訴える
- 自己評価が低く、他人と自分を比較して劣等感を抱いてしまう
- 完璧を求める傾向があり、期待に応えようとするあまり精神的に疲弊してしまう
学校生活での挫折や人前で恥をかいた経験がある子どもは、登校への抵抗感が強まる可能性があるでしょう。
タイプ4:無気力型(旧「無気力型」)
無気力型(旧「無気力型」)は、なんとなく学校に行く気がしないといった曖昧な理由で不登校になるタイプです。
このタイプの特徴は、以下のとおりです。
- 何に対しても無気力な状態である
- 学校へ行かないことへの罪悪感は少ない
- 心因性の身体症状はない場合が多い
- 家では元気で、自分の好きなことをして過ごす
- 表面的には問題がないように見えるが、強い自己否定感を抱えている
無気力型は、学校での人間関係や過度なプレッシャーなどが引き金となる場合があります。
タイプ5:人間関係型(旧「学校に起因する型」)
人間関係型(旧「学校に起因する型」)は、主に学校内での人間関係に起因する問題が原因で登校できなくなる状態を指します。
このタイプの特徴は、以下のとおりです。
- いじめやからかい、友達とのトラブルなど具体的な人間関係の問題がある
- 登校しようとする意志はあるものの、問題を一人で解決できず、登校をためらってしまう
- ストレスが積み重なり、頭痛や腹痛などの身体症状を訴える場合がある
学校でのトラブルが原因で感情が不安定になり、暴力的な行動を取る子どももいるため、早期の対応が必要です。
タイプ6:神経性障がいを伴う型(旧「神経症等を伴う型」)
神経性障がいを伴う型(旧「神経症等を伴う型」)は、主にストレスや心理的な要因の影響により不登校になっている状態を指します。
このタイプの特徴は、以下のとおりです。
- 頭痛、腹痛、吐き気、発熱などの身体的な症状を訴える場合が多い
- 自分の内的な世界にこもりがちで、几帳面な性格や主観的なこだわりを持っている
- 摂食障がいや自傷行為を伴うことがある
まれに、統合失調症などの精神疾患の初期症状として不登校になる場合もあるため、精神疾患の疑いがあるときは早期に医療機関を受診しましょう。
タイプ7:発達障がいを伴う型(旧「発達・学力遅延を伴う型」)
発達障がいを伴う型(旧「発達・学力遅延を伴う型」)は、発達障がいや学習障がいが原因で学校生活に適応できない状態を指します。
このタイプの特徴は、以下のとおりです。
- 同学年の子どもたちに比べて学力の成長が遅く、特に特定の教科において著しい困難を示す場合がある
- コミュニケーションが苦手で、友達との関係を築くのが難しい
- 教室の音や周囲の刺激に対して敏感
- 想定外のことが起きると強い不安を感じ、パニックになる
発達障がいの種類によって特性が異なるため、本人の特性に合わせた環境設定や学習支援の工夫が必要です。
不登校混合型(旧「甘え依存型」)の初期症状は?段階別の状態
不登校は、行き渋りから始まり、いくつかの段階を経て学校への再登校を目指すようになります。
ここでは、混合型の段階別の初期症状や状態を詳しく解説します。
混合型の前兆期
混合型の前兆期は、子どもが学校に対して不安や抵抗感を抱き始める段階です。
「行かなくてはいけない」と「行きたくない」という感情が交錯し、ストレスや不安で心身の疲労感が強くなります。
また、朝起きられなかったり身体的な不調を訴えたりと、登校を避けるような行動が見られます。
この時期は、無理に登校を促さず、行きたくないという子どもの気持ちを受け入れましょう。
混合型の進行期
混合型の進行期は、登校が日常的に困難になり、さまざまな心理的および行動的な変化が見られる段階です。
この時期は、生活リズムが乱れて昼夜逆転の生活になる子どもも多くいます。
また、学校や勉強の話をすると部屋へ逃げ込んでしまうなど、親や教師に対して無気力な態度を示す場合もあります。
友達との関わりも希薄になり、コミュニケーションを避ける場面が多くなるでしょう。
混合型の混乱期
混合型の混乱期は、学校に対する不安や抵抗感が続く中で、徐々に回復の兆しが見え始める段階です。
今まで閉じこもりがちだった子どもが、家族とのコミュニケーションを取るようになり、表情が明るくなります。
生活リズムにも改善の傾向が見られ、午前中に起きられるようになるでしょう。
また、外出の頻度や活動の範囲が増えていくのも、この時期の特徴です。
混合型の回復期
混合型の回復期は、子どもが学校に対する意欲を取り戻し、徐々に日常生活に戻ろうとする段階です。
この時期になると、心身の状態が安定し「学校へ行ってみようかな」という気持ちが湧いてきます。
遅刻や早退を繰り返しながらも、保健室登校や行事の参加など本人が行きやすい形での登校が可能になるでしょう。
不登校混合型(旧「甘え依存型」)のサポート方法
不登校混合型は、適切な対応により安心した学校生活が送れるようになります。
ここでは、不登校混合型の子どもに対するサポート方法を紹介します。
本人の気持ちに耳を傾ける
まずは本人の気持ちに耳を傾け、感情や思いを理解することが、適切なサポートへの第一歩です。
自分の感情を自由に表現できる環境を整え、安心して話せる状況を作れば、親子の信頼関係も深まります。
また、否定せず共感する姿勢で話を聞くと、子どもの安心感につながるでしょう。
小さな成功体験を積み重ねる
小さな成功体験を積み重ねると「できた」という感覚を実感でき、自己肯定感が高まります。
まずは日常生活の中で達成可能な目標を設定し、少しずつクリアしていきましょう。
目標をクリアした際は、しっかりと褒めて認めてあげると、モチベーションの向上につながります。
生活習慣を整える
不登校になると、寝る時間が遅くなり生活リズムが乱れがちです。
朝日を浴びたり決まった時間にしっかりと食事を取ったりと、毎日同じリズムで生活ができるようにサポートしていきましょう。
散歩や軽いランニングなどの運動も、良質な睡眠を取るためにおすすめです。
得意なことを伸ばして自信をつける
子どもが得意なことに取り組むと、成功体験が得やすくなり、自己肯定感が高まります。
保護者は、子どもが好きなことや趣味を把握し、のびのびと取り組める環境を整えましょう。
成功体験の積み重ねが大きな自信となり、新たな課題に挑戦する力となるでしょう。
学校と情報を共有し連携を図る
不登校児のケアには、学校との連携も必要です。
子どもの状況を把握し、担任の先生やスクールカウンセラーと情報を共有しましょう。
家庭と学校が協力してサポート体制を整えておくと、再び登校への意欲が見えた際に適切な支援が可能になります。
参考:文部科学省『誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策COCOLOプラン』
よくある質問
近年、不登校は年々増加してきており、どのような子どもが不登校になりやすいのか気になっている方もいるでしょう。
ここでは、不登校に関するよくある質問を解説します。
不登校になりやすい子の特徴は?
不登校になりやすい子どもには、いくつかの傾向や環境的要因があります。
- 感受性が高い:ストレスや不安に対して敏感である
- コミュニケーションが苦手:他者との関わりを避ける傾向があり、特に新しい環境や人間関係に対して強い不安を感じる
- 自己肯定感が低い:自分に自信がなく、他者と比較して劣等感を抱きやすい傾向がある
- 完璧主義:高い理想を持ちすぎるあまり、失敗を恐れて行動を起こせなくなってしまう
- 家庭環境の影響:不安定な家庭環境や親子関係の悪化が、不登校の要因となる場合がある
今学校へ行けている子どもも、年齢とともに悩みが変化していきます。
子どもの性格や特性を十分に把握し、少しでも不安な様子があれば早期に適切なサポートをしていきましょう。
不登校は何型が多い?
不登校の要因で一番多いのは「無気力型」であるという結果が、文部科学省の調査により示されています。
小・中学校の不登校児の49.7%、高校生の39.2%が無気力型で、約半数近くの生徒がこの要因に当てはまります。
また、近年では複数の要因が絡み合った複合型の不登校も増加しているため、子どもが何に問題を抱えているのか、その見極めが重要になるでしょう。
参考:文部科学省『令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について』
【まとめ】不登校混合型(旧「甘え依存型」)の特徴とサポート方法
不登校は、混合型を含む7つのタイプに分けられます。
不登校混合型は、感情の変化が大きく情緒不安定になりやすい、自己主張が苦手などの特徴があり、友人関係のトラブルも不登校を助長する原因として挙げられています。
登校への拒否が見られたら、まずは子どもの様子をよく観察し、無理に登校させるのではなく休ませて心身の回復を図るのも一つの方法です。
不登校の要因はそれぞれ異なるため、一人ひとりにあった適切な対応をしていきましょう。
TS assistは、児童発達支援・放課後等デイサービスに特化したコンサルタントとして、豊富な運営経験を活かした専門的な支援を提供いたします。200店舗以上のサポート実績に基づき、職員の信頼関係構築や業務効率化のための具体的な戦略を提案します。
各施設に合わせたカスタマイズサービスで、経営の安定と収益向上を目指しましょう。個別対応の細やかさと、Googleチャットを通じた迅速なコミュニケーションで、お気軽にご相談いただける体制を整えております。より良い療育の提供に向けて、TS assistはお客様の信頼できるパートナーであり続けます。